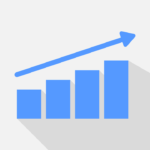2020/06/04

sponsored link
会社の業績を見る上では営業利益を重視されているが
あなたの会社の経営陣どうでしょう?
報告書類にしても売上原価と販管費を合算し
「営業費用」という科目として表示することが多いかと思います。
経営陣は、営業活動からきちんと利益を出している事を
株主や債権者に説明する必要があるため、
何としてでも営業利益を黒字としたいのです。
また、株式を多く保有する企業なら、後述する「経常利益」を
営業利益的に扱うことがあります。
金融機関は経常利益を重視している
融資を申し込んだとき、銀行の融資担当者から、
「経常利益はどれくらい出てますか?」
と聞かれた方も多いのではないかと思います。
金融機関としては、企業が経常的な事業活動から安定した利益を出せないと
融資の返済が滞ることになるわけですから、当然ですね。
このように、「営業利益」や「経常利益」は、
外部から注目される利益なため、経営陣も神経を尖らせるのですが、
売上総利益、即ち「粗利」については、
製造業の会社以外では議論の場に出てくる事が少ないのではないでしょうか?
経理的な専門職で活躍する方は、私と同じ考えをお持ちではないか、と
勝手に推測しますが、私としては、この「粗利益」こそ
一番重視すべき利益であると考えます。
そして、単に粗利益の額にこだわるだけではなく、
粗利益率をプロジェクト(現場)毎にきちんと管理する
これが重要です。
企業が目標設定する粗利益率は、業種によって異なりますが、
直接原価以外の科目についても、原価に含める経理方法を採用する企業なら
20%は確保しようとするのではないでしょうか。
直接原価だけを原価とする経理方法を採用しているなら、
30%は確保しようと考えているでしょう。
こうして、固定費を上回るだけの粗利益を産み出すには、
どれだけ受注しなければならないか、逆算していくのです。
粗利益の考え方の例
・固定費は年間10億
・粗利益率は20%
・粗利益は固定費分10億に加え、利益(所得)に対し課される税金分も
確保しなければなりません。
有利子負債があるなら、その支払利息分も確保する必要があります。
ここでは、法人税率を40%と仮定し(法人税額=4億)、支払利息はゼロとします。
そうなると、粗利益は10億+4億=14億必要ということになります。
粗利益14億を産み出す売上は
14億÷20%=70億
企業の事業計画としては、年度内に売上計上できる受注を70億以上
獲得することを設定しないといけませんね。
上記の考え方をできる経営者は製造業、建設業に多くいらっしゃいますが、
サービス業ではあまりお会いしたことがありません。
最も設定しやくすく、かつ重要性の高い「粗利益」について、
経理部門から経営陣に対し、注視する必要性について説明する必要があります。